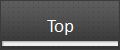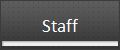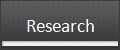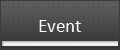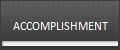研究室には教員3名、16名の学生(令和7年度は、博士課程1名(日本学術振興会特別研究員DC2)、修士課程13名、学部4年2名)がいます。
研究室の基本的な教育・研究に対する方針は
1.基礎学力を身に付けること
2.オリジナリティの高い研究に取り組むこと
3.研究者・技術者として社会性と国際性をもつこと
です。
基礎学力は研究での教員と学生との間のディスカッションを通じて、日々高めるよう努力しています。国際性を身に付けるために必要不可欠な語学力は、ゼミ発表を英語で行う等の工夫で養っています。学生たちは夏季休暇などを利用して積極的に海外へ留学しており、見聞を広めています。
すべての研究テーマは表面/界面化学と地球環境という2つのキーワードが共通しています。
類似テーマをやっている学生が必ずしも多くないため、学生が一人一人独立して研究を進める必要があり、自主性と責任感が身につきます。
3人の教員のバックグラウンドがそれぞれ異なることから、ゼミを通じて自分が取り組んでいる研究テーマとは異なる内容も勉強でき、知識の裾野が広がります。
1つ1つの研究は学生たちの努力の賜物であると考え、可能な限り論文など、目に見える形で発表するよう心がけています。
中島・磯部研究室の活動
【留学】
希望者は学内の留学制度を利用し、3ヶ月程度留学します。毎年2,3名程度が採択され、海外の大学に留学しています。
【学会発表】
通常、学部4年生から修士課程の間に2,3回程度の学会発表を行います。良い結果が出れば海外での発表もできます。
講義などの活動
2023年度以降
【講義】材料熱力学(MAT.A204)
【講義】無機表面化学特論(MAT.C408)
【講義】セラミックス概論(MAT.C205)
【講義】セラミックスプロセシング(MAT.C206)
【講義】物質理工学概論A(XMC.A102)
【講義】薄膜・単結晶プロセシング(MAT.C315)
【講義】無機エネルギー変換材料特論(ENR.J408)
【講義】物質理工学リテラシ(XMC.A101)
【講義】研究プロジェクト(MAT.Z381)
【講義】セラミックス実験第一(MAT.C350)
【講義】材料科学実験第一(MAT.A250)
【講義】材料科学実験第二(MAT.A251)
【講義】材料科学実験第三(MAT.A252)
卒業論文研究
東京工業大学・物質理工学院・材料系からは中島・磯部研究室において卒業研究を行うことができます。研究室所属の際に希望を出して下さい。
修士課程・博士課程への進学
中島・磯部研究室に進学を希望される方は、第一希望の指導教員名に「中島章」または「磯部敏宏」、学院・系に「物質理工学院・材料系」を記入してください。
大学院の受験にはTOEICのスコアが必要となります。
受験の際は事前にメールでご連絡下さい。
研究室紹介記事
セラミックス誌「研究室紹介」(PDF)
「ウイズコロナ社会への設計図 予防・診断・治療の未来」 (東工大広報)
高校生新聞Online(外部サイト)
物質理工学院材料系入学試験の概要
学内リンク
物質理工学院入試説明会
下記のとおり物質理工学院の説明会を予定しております.
学内リンク
本講座は無機材料工学科で第4番目の講座として開設され、当初は「地学教室」(末野悌六 助教授)と呼ばれていました。
その後、故山田久夫教授の時代に「地質鉱物学講座」と名称変更され、小坂丈予教授の時代には「鉱産原料講座」へと変更されました。
さらに、大津賀望教授を迎え「セラミックス原料講座」と名称変更されました。
また、本学の大学院重点化に伴う改組により当講座は坂井研究室と一緒に「無機環境材料講座」となり、研究室の名前は「地球環境材料研究分野」と変更されました。
現在はさらなる改組により物質理工学院材料系に所属する研究室となっています。
講座名の変遷からもわかるように、元来は地学・地質鉱物の分野を研究対象としてきましたが、現在では内容が変わり、
現在の研究テーマは資源・環境・エネルギーに関連した内容でセラミックスの材料設計・評価を行っています。